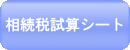受付時間 | 10:00~16:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 |
|---|
遺族の方が年金として受給されていた生命保険金のうち相続税の課税対象となった部分(相続税がかかってない場合も含む)については所得税の課税対象とはならないとする最高裁判決を受けて平成22年10月に税務上の取扱いが変更されましたが、その際に救済された部分は過去5年分(平成17年分~平成21年分)だけで、それ以前は法改正しないと救済されない状況でした。
しかし、今回平成23年6月30日施行の税制改正の中で「特別還付金」制度として救済措置が織り込まれました。
還付される対象の保険契約、対象者は平成22年10月の取扱いと同じです。特別還付金の対象となる年分は平成12年〜平成17年です。(平成22年10月の取扱変更により平成17年分の還付を受けられた方は平成17年分は対象となりません。)
該当される方は忘れずに手続きするようにして下さい。
請求期間は平成23年6月30日〜平成24年6月29日の1年間です。
【なお、この特別還付金及び加算金については、所得税及び住民税ともに非課税となります】
前回の更正の請求の際には保険会社から請求のための資料が届きましたが、この特別還付金の場合、資料を送らない保険会社が多いようです。前回送られた資料で年金の受給総額、受給期間がわかるからみたいですが、資料をなくされた方や届いていない方は保険会社等に請求する必要があります。
また還付金の金額の計算は国税庁の特別還付金請求書等作成システムで特別還付金請求書及び計算明細書を作成することができます。請求期間は1年間ですので準備が出来たらすぐに手続きするようにしてください。
なお平成18年分以降の還付手続きがまだお済みでない方はそれも合わせて手続きするようにしてください。(こちらは特別還付金の請求ではなく、通常の還付請求になりますので時間の経過とともに請求できる年分が減っていきます。)
詳しくは国税庁ホームページの
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりましたをご覧下さい。
なお、誠に申し訳ありませんがこの件に関しまして全てに対応できませんので当事務所ではお問合せを受け付けておりません。
前回もそうですが個々のご契約によって計算が異なりますし、保険会社等からの通知と国税庁の計算システムがあれば手続きできます。
なお、過年度の平成17年分から平成21年分について更正の請求や確定申告で還付請求された方は
特別還付金についての手続きについて税務署から文書が送られているようです。
手続きの詳細は最寄の税務署にお電話されて保険年金の特別還付金に関する相談であることを伝えて相談してください。
また、特別還付金に伴い還付された年分の住民税については、今のところ一部の都道府県、市町村で特別還付金に合わせた同様の給付措置を行なうようですのでお住まいの都道府県や市町村にお問合せ下さい。
個人的にはすべての都道府県、市町村で給付措置を行なってほしいと願います。
また、本来の所得税の還付金に相当するという特別還付金(給付金)制度にしているため、保険金受取人本人やその相続人しか救済されないようです。
当事務所のお客様でもいらっしゃるのですが、その当時保険金受取人がその保険について所得税の課税対象となっていたため親などの扶養から外れたケースで、通常の還付制度であればその親も扶養が増える為還付の対象となるのですが、この特別還付金制度の内容を見る限りそこまでの救済は考えていないようです。(現時点での情報を見ての私見です。)【注】平成22年10月時点の税務上の取扱いの変更情報です。
新聞やテレビでご存知と思われますが、最高裁での判決(納税者勝訴)により、相続等に係る生命契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました。
これに伴い過去のものも還付請求できますので該当する方は還付手続きを行なうようにして下さい。
◇対象となる方
ご自分が保険料を負担していない方で下記の年金を受給されている方
①死亡保険金を年金形式で受給されている方
②学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
③個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等でこうした年金が取り扱われています。
※なお、相続税や贈与税がかかるかどうかは関係ありませんので、相続税や贈与税を払われない方でも対象になります。
該当する方は、生命保険会社等から通知が来るようになっていますが、洩れもあるかもしれませんので該当するのでは
と思われる方はご契約の生命保険会社等や最寄の税務署にお問い合わせ下さい。
現在、どこの税務署もこの手続きに追われていると思いますし、電話等では判断できないと思われますので、
税務署に行かれたほうがいいと思いますが税務署の方では事前予約を勧めているようです。
また、忘れてはならないのが 還付手続きにより、その人の所得が下がり
所得金額が38万円以下になる場合には誰かの扶養になれるということです。
(平成23年6月30日施行の特別還付金制度では扶養者までの救済はない可能性が高いです。)
例えば、父親が亡くなり、その相続によって母親が年金を受け取るようになったため母親の所得が38万円を超えるので
扶養に出来なかったケースで今回の還付対象になり所得金額が38万円以下になれば母親を自分の扶養にできるなど
このような場合は年金受給者だけでなく、それによりその人を扶養にとれるようになった人も還付手続きができます。
なお、所得金額がどれぐらい下がるかは受給されている年金の内容によって異なりますのでご注意下さい。
【注】平成22年10月時点の税務上の取扱いの変更情報です (還付年分は現在のものに変更済です。)
なお、平成17年分以前については平成23年度税制改正で特別還付金制度が創設されましたので詳しくは特別還付金制度の創設をご覧ください。
今回の年金の取扱いの変更の詳細は国税庁の方に詳しく説明されていますので、このサイトでの解説は省いています。
詳しくは国税庁ホームページの
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました
をご覧下さい。
なお、現在の還付対象年度は 平成18年分〜平成22年分ですので手続きの期限は早い方は
平成23年12月31日までに平成18年分の還付請求期限が来ますので早めに手続きをして下さい。
ここでは還付手続きに関する注意点を挙げておきます。
①該当する年金であっても必ず還付になるとは限らない
加入年数が浅いなどの理由により計算しても還付にならない場合もあります。
②住民税や健康保険税が高くなる場合もある
あまりないとは思いますが、確定申告をされていない方で住民税や健康保険税の計算上もともとその年金が所得に
加算されていない(把握していないなど)場合や保険契約の内容、他の収入状況によっては、所得税は還付されますが、
住民税等が上がる場合又は所得税も上がる場合がありますのでご自分の判断で手続きして下さい。
(所得税の申告をすると同じものが市町村に行きますので。)
なお、当事務所も既存のお客様の手続きをしております最中ですので、内容や手続き等この件に関するお問い合わせは
当サイトで受け付けておりませんのでご了承下さい。
受給されている(いた)保険会社等から年金支払情報などの通知が届いたら
まずは国税庁ホームページにある保険年金の所得金額の計算のためのシステム
又は特別還付金請求書等作成システムでご自分の雑所得の金額を計算して見てください。
保険会社等からの年金支払情報などに入力に必要な情報が書いてあると思いますので
間違えないように入力して雑所得の金額が申告した金額より減っていれば還付になります。
この年金等に係る源泉徴収額がある方で確定申告をされていない方は、確定申告書を作成してみて
還付になるかどうか確認して見てください。その時住民税や健康保険税のこともお忘れなく。
お問合せ・ご相談はこちら
担当:澄田
受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日
誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市・山口市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 周南市・下松市・光市他山口県全域及び北九州、広島 (相続・事業承継業務は全国対応) |
|---|