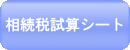受付時間 | 10:00~16:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 (事前予約で対応可) |
|---|
所得税の確定申告とは?
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得に対する税金を自ら計算して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税することとなっています。
確定申告とは1年間に得た所得に対する税金を確定し、源泉徴収や予定納税で納めた税金と比較し、過不足を精算する手続きをいいます。
確定申告は、必ずしなければならない場合と、しなくてもいいが確定申告すれば税金が戻る場合があります。参考として下記項目をご覧下さい。
確定申告をしなければならない人は?
【各種の所得金額の合計額から所得控除額を差し引いて計算された所得税額】が
【配当控除及び年末調整で控除を受けた住宅借入金等特別控除の額】より多い人です。
【各種の所得とは?】
所得税では、所得をその所得の発生形態によって以下の10種類に分けそれぞれの所得の性質に応じた計算方法により所得金額を計算するようになっています。
| 利子所得 | 配当所得 | 不動産所得 | 事業所得 | 給与所得 |
| 譲渡所得 | 一時所得 | 雑所得 | 山林所得 | 退職所得 |
【所得金額の合計額とは】
確定申告の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は適用しないで計算した各種の所得金額の合計額をいいます。
1.事業所得や不動産所得がある人
事業所得や不動産所得の所得金額とは、売上や賃貸収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。
その事業所得や不動産所得と他の所得の合計額が所得金額の合計額になりますので、その所得金額の合計額から配偶者控除、扶養控除、基礎控除、その他の所得控除額を差し引いて計算した税額が配当控除額よりも多い人は確定申告をしなければなりません。この判定で確定申告をしなくてもよい場合でも青色申告の方は以下の注意が必要です。
※ 青色申告特別控除65万円控除を受けられる方は、確定申告書の記載、貸借対照表、損益計算書その他の明細書の添付が必須要件ですので必ず申告期限内に確定申告書を提出しなければなりません。青色申告特別控除についてはこちらをご覧ください。
※青色申告特別控除10万円控除を受けられる方は、確定申告書の記載が必須要件ではありませんが、提出をしなくてもいいという根拠が明記されていませんので確定申告書の提出をお勧めします。
※ 不動産所得で優良賃貸住宅の割増償却を適用される人は確定申告書への記載が要件となっていますので不動産所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
2.給与所得がある人
給与所得者の場合は通常、年末調整によって所得税額が精算され確定しますので改めて確定申告をする必要はありませんが、他に所得がある場合などによりその年分の各種所得金額の合計額から基礎控除その他の所得金額を差し引いて計算した税額が配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いても残額がある方で次に該当する場合には確定申告をしなければなりません。
①その年分の給与の収入が2000万円を超える人(この場合は年末調整の対象となりません)
②給与等を1ヶ所から受けている人で、その給与等について源泉徴収または年末調整を受けている場合に給与所得や退職所得以外の各種所得(例えば、地代、家賃、原稿料など)の金額の合計額が20万円を超える場合
③給与等を2ヵ所以上から受けている人で、その給与等について源泉徴収または年末調整を受けている場合で、年末調整をされなかった方の給与等の収入金額と給与所得(年末調整されたもの)や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
ただし、すべての給与の収入金額が【150万円+所得控除額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)】 以内で、かつ給与所得や退職所得以外の各種所得が20万円以下である人は確定申告をする必要はありません。
④災害を受けた人で、その年分の給与についての源泉徴収税額の徴収の猶予や還付を受けられた人
⑤その他一定の場合で所得税を源泉徴収されないこととされている人や居住者で国外の給与等又は退職手当等の支払を受ける人で所得税の額が配当控除の額を超える人
(注)上記②、③の20万円の基準については以下注意する必要があります。
・同族会社の役員やその親族などで、その法人から給与のほかに、貸付金の利子、地代、家賃や機械器具などの使用料などの支払を受けている人は20万円以下であっても確定申告をする必要があります。
・住宅借入金等特別控除などを初めて受ける場合には確定申告をする必要があります。
・医療費控除等を受けるために確定申告をする場合にはこの20万円以下の所得も合わせて申告しなければなりません。
この20万基準の制度は本来確定申告をすべきですが20万程度なら確定申告をしなくてもいいというものですので、確定申告を自らする場合には金額に係わらずすべての所得を申告する必要があります。
・青色申告特別控除を受けられる人、優良賃貸住宅の割増償却を適用される人は給与等以外の他の所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。
3.退職所得がある人
退職所得は通常の場合は税額を計算されて課税関係が完結しますので確定申告する必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で所得税を源泉徴収をされた人などでその源泉徴収税額が正規に計算した場合の税額よりも少ない場合は確定申告をしなければなりません。
なお、20%の税率で源泉徴収された場合でその源泉徴収税額が正規に計算した税額よりも多い場合には確定申告をすることにより、所得税が還付になります。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して課税関係が終了した場合でも他の所得がなく所得控除が多いなどのときは確定申告をすれば所得税が還付になるケースもあります。
4.死亡、又は出国の場合
①確定申告書を提出すべき人が、亡くなった場合にはその亡くなった人の相続人が確定申告をしなければなりません。
詳細は準確定申告についてをご覧下さい。
②確定申告書を提出すべき人が出国する場合には納税管理人の届出をする場合を除き、出国の時までに申告しなければなりません。
確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっているときは、還付を受けるために申告書を提出することができます。
いわゆる還付申告と呼ばれますが、手続きや申告書は通常の確定申告と同じです。ただし、還付申告ができるのは翌年1月1日〜5年間できますので確定申告時期よりも早めに提出すれば混雑が避けられ、また還付される税金も早く戻ってくると思います。
給与所得者等の還付申告についても合わせてご覧下さい。
1.給与所得や退職所得のある人で年末調整で控除されない所得控除等がある場合
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、初年度の住宅借入金等特別控除等などは年末調整で控除することができません。
これらに該当するものがある場合には確定申告をすることにより戻る可能性があります。
2.給与所得者で年の途中で退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けなかった場合
給与の源泉徴収税額は、その月額の給与が1年間続くとしたら年額の所得税がこれぐらいで月額にするとこれぐらいという考えで決まっていますので年の中途で退職し、その後収入がないなどの場合は源泉徴収税額を納めすぎていることになりますので確定申告をすることにより戻る可能性があります。
3.収入が少ないのに源泉徴収されていたケース
配当や原稿料収入などは源泉徴収されますが、その他の所得がない場合や少ない場合などは源泉徴収による所得税が納めすぎていることになりますので確定申告をすることにより戻る可能性があります。
いろいろなケースがありますが、基本的に源泉徴収された金額や予定納税した金額がその人の所得金額から計算された所得税の年税額より多い場合は確定申告をすることにより還付されます。
申告書ソフトやe-Taxなどで仮に確定申告書を作成されることをお勧めします。
それで還付額が出れば確定申告をすれば戻ってくることになります。
退職所得などがある方は、それで課税関係が終わっているから関係ないと思われがちですが所得控除の金額によって還付になるケースもあります。
所得税と住民税では所得控除額が違うのをご存知でしょうか?
所得税がゼロ(年税額)なのに住民税の所得割が発生したという話はよくあることで、所得税がかからないから住民税もかからない(均等割等は除きます)と思われている方が多いと思いますが、医療費控除、社会保険料控除など以外のほとんどの所得控除で金額が異なります。
給与は103万までなら大丈夫というのは、所得税の扶養になれるかどうかと所得税がかかるかどうかのラインですので住民税の所得割までかからないのは扶養者がいない一般的な場合は給与収入で100万がラインになります。(控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は計算が異なりますのでご自分の市町村で確認してください)
※令和3年分から非課税判定の基準となる金額が35万円から45万円に上がりますが、給与所得者の給与所得控除額の最低ラインが65万円から55万円に下がりますので住民税の非課税ライン100万円は変わらないことになります。
詳しくは 住民税が非課税になる人をご覧ください。
【差のある所得税額控除比較表】
| 所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 | 備 考 |
| 生命保険料控除 | 12万円 (最高) | 7万円 (最高) | |
| 地震保険料控除 | 5万円 (最高) | 2万5千円 (最高) | |
| 障害者控除 | 27万円 (40万円) ※ 同居特別障害者は 75万円 | 26万円 (30万) ※ 同居特別障害者は 53万円 | ( )は特別障害者の場合 障害者控除について詳しくはこちら
|
| 寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | |
| 寡婦控除 | 27万円 (35万円) | 26万円 (30万円) | ( )は特別の寡婦の場合 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | |
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 |
|
| 扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | |
| 扶養控除(同居老親以外の老人) | 48万円 | 38万円 | |
| 扶養控除(同居老親) | 58万円 | 45万円 | |
| 配偶者控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 配偶者控除が適用出来ない場合 に配偶者特別控除の適用が できます。(要件有) |
| 配偶者控除(老人) | 48万円 | 38万円 | |
| 配偶者特別控除 | 38万円 (最高) | 33万円 (最高) | |
| 基礎控除 | 38万円 (48万円) | 33万円 (43万円) | ()は所得税については2020年分 住民税については2021年分から なお、合計所得金額が2400万超の場合は金額が変わります。 |
他の所得控除(寄付金控除を除く)については所得税と同じになります。
※平成23年分の所得税から下記の点が変わっていますのでご注意ください。
扶養控除(一般)・・・16歳以上の扶養親族に限られます。
扶養控除(特定)・・・・扶養控除対象者のうち19歳以上23歳未満の者をいいます。
子ども手当と引き換えに16歳未満の扶養控除が廃止されていますのでご注意ください。
(注)障害者控除は16歳未満であっても適用できます。
上記のような差がありますので、所得税がかからないからあとはいいやと思って計算を終わるのではなく住民税のことも頭にいれて他に使える所得控除を探してみてください。
よくあるのが、医療費控除は使えるぐらい医療費の支払いはあるけど、面倒だし所得税はかからないからしないというケースです。医療費控除については→医療費控除についてをご覧ください。
Q 住民税が非課税となる仕組みがよくわかりません。給与所得者の場合、所得税は給与収入が103万円までかからない(所得控除がない場合)と思いますが、住民税ではいくらまでならかからないのでしょうか?
A 給与所得者で一般的な方の場合は他に所得控除がない場合は100万円までは住民税が非課税となります。(住民税の所得割。均等割は市町村によって異なります)
1.非課税に該当するかどうか(所得割、均等割それぞれ別の判定になります)
2.非課税に該当しない場合に住民税の計算を行う
①障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
②生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
③前年中の総所得金額が次に掲げる金額以下の人
→同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合・・・35万円
→同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+32万円
※同一生計配偶者・・・生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下の配偶者(本人の事業専従者でないこと)
※総所得金額、合計所得金額・・・給与所得者で他に所得がない場合は給与収入から給与所得控除額を引いた金額になります。
・均等割が非課税になる方はは下記に該当する方になります。
①上記の所得割が非課税になる方の①、②に該当する人
②前年中の合計所得金額が次に掲げる金額以下の人
→同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合・・・35万円
→同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)×35万円+21万円
※上記均等割の判定の35万円、21万円の金額は地域によって異なりますのでご自分の住所の市町村等での金額をご確認ください。
ただし、給与所得控除も最低額が10万円下がりますので、給与所得の方の場合は単身者の場合、給与収入が100万円というところは変わりません。
住民税の所得控除は所得税と異なるものが多いです。
なお、所得割の非課税に該当しない場合でも所得控除等をした結果住民税はゼロになる場合もあります。(均等割は発生します)
詳しくは所得税と住民税の所得控除額の違いをご覧ください。
所得税(住民税)の確定申告の所得控除の中に障害者控除というものがあります。
障害者とは?
精神上、身体上一定の障害がある人をいいます。
詳しくは国税庁HPの障害者控除をご覧ください。
障害者手帳などある場合は判断しやすいのですが、そうでない場合は判断に迷うことが多いと思います。ここでは、国税庁のHPに書いてある障害者の要件で判断しにくいものを説明します。
POINT1 いわゆる寝たきりの状態とはどのような状態をいうのか?
具体的には、その年の12月31日において、引続き6ヶ月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ、自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいいます。特に証明書等の義務はありませんが、多くの場合判断に迷いますので、当人が65歳以上の場合、市町村ではそのような方のために障害者控除対象者認定書というものを発行してくれます。住所地を所轄する市町村に問い合わせてみてください。
POINT2 成年被後見人は特別障害者控除を受けることができる?
認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない者について、その本人の権利を守る制度である成年後見制度によって成年後見人がついた方はその状況が続く間は特別障害者控除を受けることが出来ます。この場合には後見開始の審判の事実を証明する登記事項証明書で証明することが出来ます。
| 所得税 | 住民税 | |||
| 誰が障害者?→ | 本 人 | 扶養親族(配偶者含む) | 本 人 | 扶養親族(配偶者含む) |
| 障害者控除 | 27万円 | 27万円 | 26万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者控除 | ─ | 75万円 | ─ | 53万円 |
※1 扶養親族・配偶者が障害者の場合には上記の障害者控除にそれぞれ扶養控除、配偶者控除を受けることが出来ます。(配偶者は同一生計配偶者)
※2 16歳未満の扶養親族の場合は扶養控除の適用はありませんが、障害者控除の適用はありますので忘れずに適用してください。
お問合せ・ご相談はこちら
担当:澄田
受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日
誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 周南市・下松市・光市・防府市他山口県全域 (相続・事業承継業務は全国対応) |
|---|