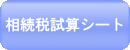受付時間 | 10:00~16:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 (事前予約で対応可) |
|---|
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者(一定要件あり)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自分の居住用の一定の家屋の新築や取得、一定の増改築をしてその3月15日までに居住する場合(その日までに居住できない場合は遅滞なく居住することが確実と見込まれる場合も含みます)にはその贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定額まで贈与税が非課税となります。
流れで説明しますと
①父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける
②贈与を受けた翌年の3月15日までに自分の居住用の建物を新築又は取得する
(一定の増改築でもOK)新築又は取得についてはこちらをご覧ください。
③贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する。
(その日までに居住が無理でも遅滞なく居住することが確実であればOK)
④贈与税の申告期限内に必要書類を添付した贈与税の申告をする
贈与を受けた翌年の3月15日まで(必ず申告が必要です)
(必要な書類の提出・手続きをすることが要件ですので事前に必要書類・手続きを確認して漏れのないようにして下さい。)
【受贈者の要件】
①贈与時に日本国内に住所を有すること
(住所を有していない場合であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることが可能)
②贈与時に贈与者の直系卑属であること
③贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
④贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)
⑤平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)
⑥自分の配偶者や親族など一定の特別の関係がある人からの住宅等の取得や請負による新築、増改築ではないこと
⑦贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
以上のすべての要件を満たすことが必要となります。
【非課税限度額】贈与者ごとに下記の金額
省エネ等住宅の場合 ・・・ 1000万円まで
その他の場合 ・・・ 500万円まで
※適用対象となる住宅用家屋の床面積は40㎡以上240㎡まで。(その家屋の2分の1以上が受贈者の居住用であること)
※省エネ等住宅とは?
家屋の区分に応じて次の表の3つの性能のいずれかの基準に適合する家屋であること
| 家屋の区分 | 省エネルギー性能 | 耐震性能 | バリアフリー性能 |
| 新築又は建築後使用されたことのない住宅 | 断熱等性能等級5以上、かつ、一次エネルギー消費量等級6以上 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) 2以上又は免震建築物 | 高齢者等配慮対策 等級(専用部分)3以上 |
| 建築後使用されたことのある住宅又は増改築 | 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上 |
※断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準は除かれます。
該当するものについてそれぞれの証明書が必要になりますが、この部分は税理士にはわかりませんので購入先、建築先の事業者に確認をして下さい。
【一定の家屋の新築・取得、一定の増改築】
新築や取得の場合や中古取得、増改築の状況に応じて上記の他、それぞれ要件があります。
取得や請負契約をする相手先や最寄の税務署に事前に確認されることをお勧めします。
一定の新築や取得等と一緒に土地や借地権を取得する場合にはそれも家屋と同様に扱うことができます。
なお、いずれの場合も取得する相手や請負契約を結ぶ相手が一定の親族などの場合にはこの特例の適用はありませんのでご注意下さい。
この特例は暦年課税でも相続時精算課税でも適用できます。
【暦年課税を選択する場合】
他に贈与をうけた物がなければ、この特例の非課税枠と通常の特別控除110万円の合計額まで非課税になり、それを超える金額に贈与税がかかります。
【相続時精算課税を選択する場合】(相続時精算課税制度についてはこちらをご覧下さい)
最初にこの特例の非課税制度を適用して、非課税枠を超える部分について相続時精算課税制度を適用するようになります。
【土地の先行取得】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠措置等について
適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される
土地等を取得する場合のその土地等の取得資金も入ります。
詳しくは土地を先行取得した場合の注意点をご覧ください。
Q 贈与税の住宅取得等資金の非課税の特例は、大前提の要件として、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅用家屋を新築、又は取得等することですが、3月15日までに引き渡されていない場合はどうなるのでしょうか?
A 贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築、取得等をしていない場合にはこの特例を受けることはできません。なお、新築又は取得等とはどの状態のことをいうかは住宅家屋の種類によって下記のようになります。
①分譲マンションや建売住宅の場合
この場合は請負契約ではなく売買契約になりますので基本的には贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを受けることが必要です。
②請負契約による新築、増改築の場合
この場合は贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡し等までいかなくても、要件である「新築」には下記の状態も含まれます
◇新築・・・屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態
◇増改築・・・屋根(その骨組みを含みます)を融資、既存の建物と一体となって土地に定着した建造物として認められる状態
屋根を有し、土地に定着した状態はどのような状態かといいますと、一般的には棟上げが終わった状態をいいます。
なお、上記の状態までに行かない場合にはこの特例を受けることはできませんので事前にしっかりスケジュールを組んでおく必要があります。
【新型コロナウィルス感染症が原因で工期が遅れた場合】
この度の新型コロナウィルス感染症により、資材、機材の調達遅れや感染者の発生、施工業者の休業などによって施主に原因がない場合などは災害に基因するやむを得ない事情に該当するものとされ従来の新築等の期限が1年延長されます。
Q 住宅を新築する場合に敷地である土地を先に購入する予定ですが、贈与を受けた金銭をその土地の取得に充てた場合、住宅取得等資金の贈与の特例は受けることができますか?
A 贈与を受けた金銭を土地の取得に充てた場合も贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築すれば特例の適用を受けることが出来ます。
住宅を新築する際には、建売住宅以外の場合は土地を先行取得するケースがほとんどだと思います。
この住宅取得等資金の贈与の特例は住宅とともに取得する土地の購入資金についても適用がありますが、先行取得した土地についてもその後住宅を建築すれば対象になります。
ただし、土地を取得して住宅を建築する期間には制限がありますので注意する必要があります。
この特例は贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築又は取得することが要件になります。そのため、贈与を受けた金銭を土地の取得に充てた場合には必ず翌年の3月15日までにその敷地の上に住宅用家屋が新築されている必要があります。
資金の贈与を受けて土地を購入し、建物を建築する計画の際にはそのスケジュールをしっかり確認する必要があります。
土地を取得したあと、住宅用家屋の建築が間に合わないような可能性があれば贈与資金を土地に充てるのはあきらめて土地は贈与資金ではなく自己の資金や借入で土地代金を支払うなどの検討も必要になります。
新築についてはこちらをご覧ください。
この度の新型コロナウィルス感染症により、資材、機材の調達遅れや感染者の発生、施工業者の休業などによって施主に原因がない場合などは災害に基因するやむを得ない事情に該当するものとされ従来の新築等の期限が1年延長されます。
お問合せ・ご相談はこちら
担当:澄田
受付時間:10:00~16:00
定休日:土日祝祭日
誠に申し訳ありませんが、医療費控除等、お電話でのご質問は受け付けておりません。
相続でお悩みの方をサポートする山口県周南市の税理士です。
周南市・下松市・光市・防府市を中心に活動していますが山口県以外の他の地域も対応可能です。
相続税の申告、贈与、相続対策、不動産評価、株式評価、譲渡所得等、セカンドオピニオンとしても対応していますので顧問税理士がいらっしゃる方もお気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 周南市・下松市・光市・防府市他山口県全域 (相続・事業承継業務は全国対応) |
|---|